- ホーム
- プロジェクトマネジメントのヒント
- プロジェクトを失敗させないヒント69『「負けるが勝ち」のマネジメント』
プロジェクトを失敗させないヒント69『「負けるが勝ち」のマネジメント』
『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』とは
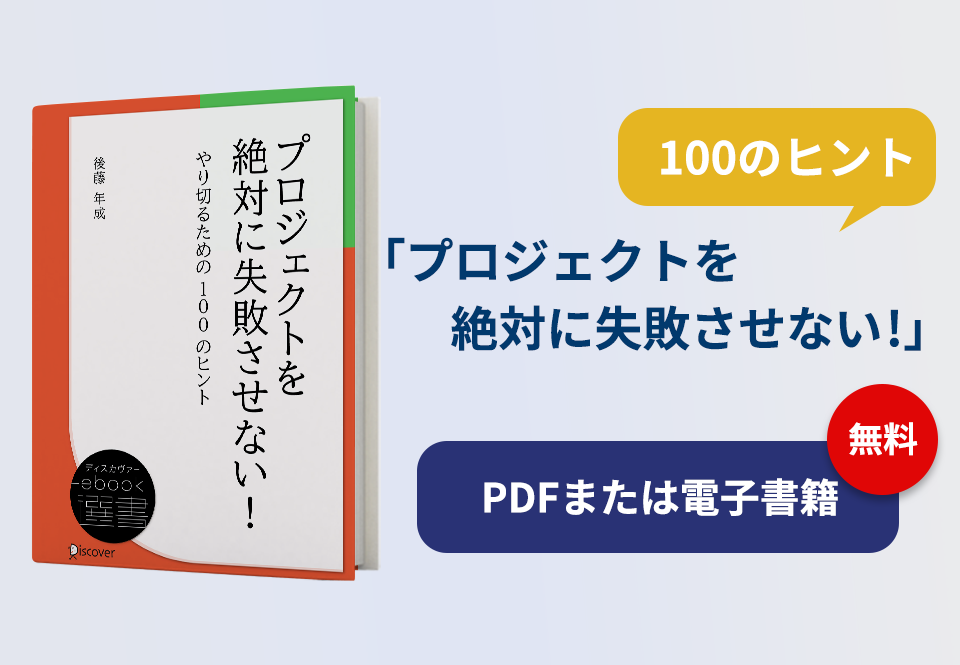
本記事は、プロジェクトを成功させるために必要なノウハウを、数百の支援実績経験をもとに記述した『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』より、 1つずつヒントをご紹介していく企画です。プロジェクトマネジメントについて、何らかの気づきを得るきっかけになれば幸いです。
当社はプロジェクトマネジメントの知識と経験を有し、皆様のプロジェクトが成功するお手伝いをさせていただいております。 プロジェクトマネジメントに関する疑問や課題がある方、成功への道筋をお探しの方、どうぞお気軽にご連絡ください。
お問合せはこちらからどうぞ。
※『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』をPDFまたは電子書籍でダウンロードできます
プロジェクトをマネジメントする立場にいる人は、メンバーとの接し方を一歩間違えると、現場から強い反発を受けて孤立してしまいます。最悪なパターンは、地位の高さや経験の豊富さを武器に、メンバーを常にやり込めてしまうこと。これが感情的な対立に発展すると、プロジェクトの成功はおぼつかなくなります。
私が一貫して述べていることは、「プロジェクトのメンバーが気持ちよく作業できる環境を作ること」がPMOの一番の任務だということです。ここで言う環境とは、仕組みや運用ルールだけでなく、メンバーが気持ちよく作業できる雰囲気や気持ちも当然含みます。
勝ってばかりいると相談されなくなる
PMOとしては、時としてメンバーに対して耳が痛くなるような嫌なことも言わなければなりません。そんな時でも、PMOとメンバーの意見が対立した時には「相手にいつも勝っていてはNGだ」と考えることが重要です。
私の実体験を話します。進捗会議で「なぜ、遅延しているんだ」「そのキャッチアッププランで本当に追いつけるのか」「遅延している原因は正しいのか」など、メンバーを追い詰め過ぎてしまったことがあります。すると次の進捗会議から、不都合な情報が隠されてしまい、重要な情報が上がってこなくなりました。
この時のメンバーは、個人の能力がないと批判されているように捉えてしまったようです。そんなつもりはなかったのですが、結果的にはPMOに対して敵意を抱かれかねない状況でした。PMOという仕事柄、どうしても好かれる立場にはありませんが、敵意を抱かれたら大変です。プロジェクトに必要な情報が隠されてしまうだけでなく、プロジェクト内に感情の対立が生まれ、雰囲気がどんどん悪くなってしまいます。
PMOは「2勝3敗」ぐらいがちょうどいい
プロジェクトには当然、様々な対立が発生します。必要なQCDの決定事項が対立する際には、教科書通りに対立をあぶり出し、しっかりとマネジメントすることが必要です。しかし、これが感情の対立に発展してしまうとコミュニケーションが分断されてしまい、プロジェクトが傾く原因になります。
PMOとメンバーそれぞれの地位や経験は、大体において「PMO>メンバー」となることが多いでしょう。すると意見が対立した時、PMOの意見がいつも勝ってしまうのです。
そんな状況が続くと、メンバーの心には不満がたまっていき、「どうせ何を言ってもPMOの言う通りにするんでしょ」という気持ちがメンバーにわいてきます。これはメンバーの主体性を奪うことになり、ひいては「言われたことを言われたままにやるだけ」といった事態を引き起こしかねません。そうなってしまったら、プロジェクトのメンバーが気持ちよく作業できる環境ではなくなります。メンバーがPMOにどんな感情を抱いているかは察しがつくでしょう。
私がPMOとして駆け出しだった頃の失敗から学んだことは、「PMOとして負けてあげる」ことの重要性です。負けてあげるとは、相手の意見を十分に尊重する、相手の意見を基にして考えを発展させることです。
メンバーはプロジェクトの成功という共通目標を持っています。対立が起こるのは、目標を達成するための「前提事項」や「進め方」が対立するためです。PMOには「今までこのやり方で成功してきたから、次もこうするべきだ」という考えがあるかもしれません。しかし、たまには相手の意見を受け入れるだけの余裕を持つことも大切です。
注意が必要なのは「譲れないところは、決して譲ってはいけない」ということ。例えば、品質第一で進められているプロジェクトで、進捗の遅れが目立ち始めたとします。遅れを取り戻すため、あるメンバーが「品質を担保するための工数を減らしたい」と主張してきても、PMOは突っぱねなければなりません。
Lose But Finally Win.
いざという時にPMOが勝っても、不満を残さないようにするには、普段の対立において譲れるところは譲り、気持ちの上で“貸し”を作っておくことです。PMOには「Lose But Finally Win.」(負けても最後に勝つ=プロジェクトが成功する)という心づもりが必要でしょう。
PMOがメンバーとの感情的な対立を起こさないためのポイントとして、画一的なマネジメントを強制しないことが挙げられます。プロジェクトルールとして最低限守らなければならないことは別として、各メンバーに応じたマネジメントができるように、ある程度の柔軟性を持たせてあげます。
進捗の遅れが発生した時、あるリーダーは「PMOと一緒になって遅れを挽回するプランを考えたい。PMOに原因を分析してほしい」と思っているかもしれません。別のリーダーは「チーム内の進捗にいちいち口を出してほしくない。リーダーとして責任を持ってキャッチアップするから、結果だけ見ていてほしい」と考えているかもしれません。
前者の場合であれば、PMOは積極的に関与してリードしていきます。後者の場合は、経過を観察してキャッチアップの傾向が見られれば、そのまま状況だけ観察していきます。もちろん、何週間も改善が見られない時はPMOとして介入しますが、最初から口を挟むと、任せた結果を見てから介入するのとでは、リーダーの納得感が全然違います。
