- ホーム
- プロジェクトマネジメントのヒント
- プロジェクトを失敗させないヒント73『なぜなぜ5回が雰囲気を悪くすることも』
プロジェクトを失敗させないヒント73『なぜなぜ5回が雰囲気を悪くすることも』
『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』とは
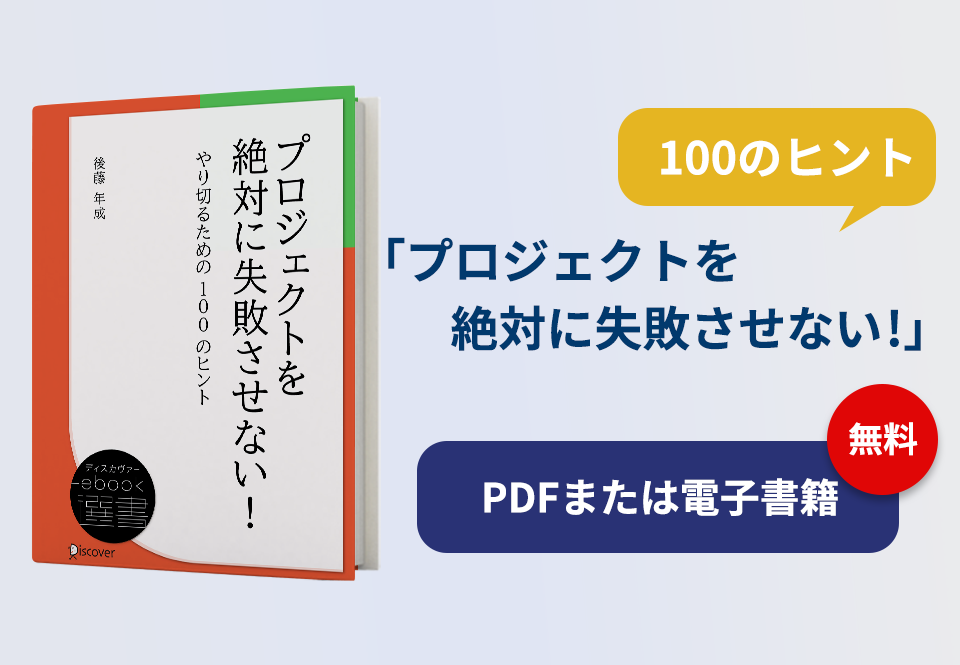
本記事は、プロジェクトを成功させるために必要なノウハウを、数百の支援実績経験をもとに記述した『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』より、 1つずつヒントをご紹介していく企画です。プロジェクトマネジメントについて、何らかの気づきを得るきっかけになれば幸いです。
当社はプロジェクトマネジメントの知識と経験を有し、皆様のプロジェクトが成功するお手伝いをさせていただいております。 プロジェクトマネジメントに関する疑問や課題がある方、成功への道筋をお探しの方、どうぞお気軽にご連絡ください。
お問合せはこちらからどうぞ。
※『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』をPDFまたは電子書籍でダウンロードできます
プロジェクトを進めるにつれ、なかなか解決しない課題が山ほど出てきます。「この課題が解決しない原因は何か」といった具合に「なぜ? なぜ? なぜ?」を突き詰めていくと、かえってプロジェクトの雰囲気を悪くしてしまうことがあります。改善活動に必須の「なぜなぜ分析」も、プロジェクトでは問題に合わせた使い方をしなければなりません。
問題を解決しようと「なぜ? なぜ? なぜ?」と問題の原因分析をしていくことは、いわゆるトヨタ流のカイゼンやQC(品質管理)サークルといった形で、多くの企業やプロジェクトで実践されています。問題を解決する活動以外にも、企画書を上司に出す際に「ここはなぜ? それはなぜ? どうして?」と繰り返し聞かれた経験がある人は多いでしょう。
「なぜ?」を繰り返すことは、理屈が通っていなければならないビジネスの世界では当たり前の習慣です。プロジェクトの現場でも「なぜ?」が重要なのは同じです。進捗会議の場で多くの人が、次のような場面に遭遇しているはずです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
PMO:画面設計の進捗が計画通りに進んでいないようです。
プロジェクトマネジャー:それはまずいな。原因は何か。
チームリーダー:当初想定していたよりも画面の難易度が高いため、思うように作業が進んでいません。
PMO:当初想定していたよりも難易度が高かった画面は、何画面あるのですか。それらは、どのように難易度が高かったのですか。
チームリーダー:数はすぐには分からないので、あとでご報告します。
プロジェクトマネジャー:ついでに、当初の画面難易度の見積もりとズレが生じている理由は何かな。現時点で作業に取りかかっていない画面でも、同じようなズレが発生するかもしれないよね。
チームリーダー:それについても、後ほどご報告します。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
問題を深掘りしていく際、解決しようと思えば思うほど、徹底的に原因を追究しようとします。「なぜを繰り返せ」と号令をかけられている現場なら、呪文のように「なぜ?」を繰り返してみるものです。こうした習慣が良い結果をもたらすことに異論はないでしょう。
「なぜ?」は人や組織から反発を受けやすい
しかし、問題にも色々な種類があります。物の製造に関する問題の改善やシステムの問題は、緻密に分析していくことで原因をつぶすことができ、結果として問題が解決されることが多いでしょう。
一方で、プロジェクトでは物の製造やシステムの問題よりも、「人」「人のつながり」「組織」に関係する問題の方が大きく横たわっています。そして人や組織の問題は「なぜ?」を繰り返すことで問題を突き止めれば解決できるほど、単純ではありません。人や組織は、自分が悪いとされただけで反発心が生まれ、「自分が悪いのではなくて、××が悪い」と自己防衛してしまうケースが多々見られます。
あなたのプロジェクトで「○○部の協力がうまく得られていない」といった問題が起こったとしましょう。原因追究型の「なぜ?」を連発すると、次のような状況に陥ることがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
PMO:なぜ○○部の協力がうまく得られていないのですか。
業務チームリーダー:○○部のAさんの時間が取れないのです。
PMO:なるほど。Aさんの時間が取れないのはなぜですか。
業務チームリーダー:○○部の部長に支援の取り付けをお願いしていますが、それが甘いからだと思います。
PMO:なぜ部長への支援の取り付けが甘いのですか。
業務チームリーダー:うちのチームのBさんの働きかけが足りないからだと思います。
PMO:それなら、Bさんの働きかけを改善してもらえば解決しますね。
業務チームリーダー:そうかもしれませんが、Bさんの担当ではない領域のタスクも支援しなくてはならなくなったので、工数が取れていないんです。むしろ、悪いのはBさんではなく、人が足りないというプロジェクトの状態だと思います。何とかしてください。
PMO:そんなこと言われても、予算とスケジュールがあるんですよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の場合、予算やスケジュールの配分をマネジメントできれば解決できますが、会話の最後でプロジェクト全体の人手不足の話題に問題がすり替えられてしまいました。こうなると堂々巡りです。「それでは継続検討ということで」となりがちです。問題が解決しないばかりか、話がこじれて、いつまでたっても解決しない、という事態になる危険性もあります。
やっかいなのは人間関係まで悪化して、プロジェクトの雰囲気を悪化させてしまうことです。故障して止まった機械は黙って修理を待ちますが、人は「悪いのはあなただ」と言われてしまうと、「反発感情→人間関係の悪化→プロジェクトの雰囲気悪化」というように、悪い感情がじわじわとプロジェクト全体に伝播していきます。人間関係の悪化とプロジェクトの雰囲気悪化が起こると、生産性の低下はもとより、プロジェクト崩壊の一因になります。
こういった組織問題の原因を「なぜ? なぜ?」と分析していくと、その最小単位である「人」の問題に必然的にたどり着きます。それがあつれきを生む原因にもなります。
人を追及しないための発想の転換
では、人の問題にどう対処すればよいでしょうか。原因追究型の「なぜ?」ではなく、解決志向の「どうやって?」を使うのです。近年注目されているコーチングやソリューションフォーカスといったポジティブアプローチもそうですが、問題の原因追究よりも「手に入れたい状態」を「どのように実現するか」を考えるのが解決志向です。
解決志向で問題に当たる場合、原因となっている人や組織を追及することなく、どうすれば一緒に実現できるかを検討していけるようになります。プロジェクトで「○○部の協力が得られていない」という問題が起こった時は、次のような感じで「どうやって?」を使いましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
PMO:○○部の協力が得られている状態って、どんな感じかな。
業務チームリーダー:積極的に前向きに協力してくれている感じですね。
PMO:確かにそうだね。前向きな感じって、どうすれば作れますか。
業務チームリーダー:まず、仲良くなることじゃないですか。あとは、プロジェクトに対して理解してもらっている感じですよね。
PMO:なるほど。どうやったら、もっと仲良くなれるかな。
業務チームリーダー:色々あると思いますが、とりあえず、今晩にでも○○部の部長さんと飲みに行って、終電まで語り合いましょうか。
PMO:そりゃいいね。じゃ、私たちも行くので、早速やってみましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の原因はコミュニケーション不足で、対応策は非公式なコミュニケーションの実施、という見方をすることも可能かもしれません。ただ、原因追究型で検討した場合には、誰かのせいで終わってしまうかもしれません。
PMOの役割はプロジェクトの成功を目指し、円滑にプロジェクトを進めるためのサポートをすることです。犯人捜しをして、プロジェクトの雰囲気を悪化することではありませんし、そんなことは誰も望んでいません。
プロジェクトの雰囲気を明るくし、プロジェクトを成功させるために、問題志向だけではなく「解決志向」の考え方も取り入れてみてはいかがでしょうか。
