- ホーム
- プロジェクトマネジメントのヒント
- プロジェクトを失敗させないヒント77『問題の解決速度を高めるコツ』
プロジェクトを失敗させないヒント77『問題の解決速度を高めるコツ』
『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』とは
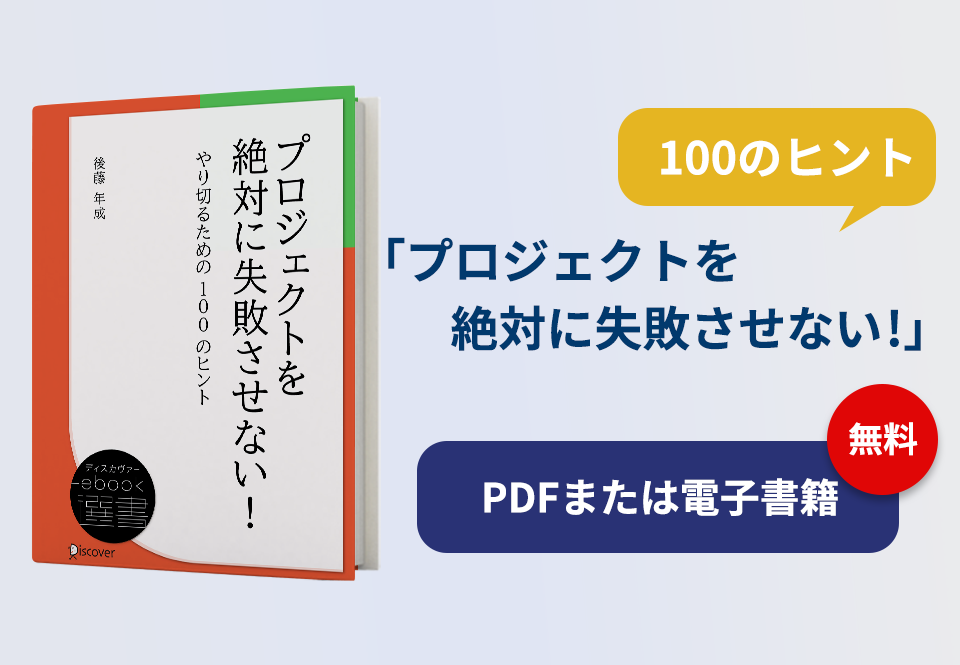
本記事は、プロジェクトを成功させるために必要なノウハウを、数百の支援実績経験をもとに記述した『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』より、 1つずつヒントをご紹介していく企画です。プロジェクトマネジメントについて、何らかの気づきを得るきっかけになれば幸いです。
当社はプロジェクトマネジメントの知識と経験を有し、皆様のプロジェクトが成功するお手伝いをさせていただいております。 プロジェクトマネジメントに関する疑問や課題がある方、成功への道筋をお探しの方、どうぞお気軽にご連絡ください。
お問合せはこちらからどうぞ。
※『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』をPDFまたは電子書籍でダウンロードできます
問題が起こらないプロジェクトなどありません。しかし、「問題の発生速度 < 問題の解決速度」という状態である限り、問題は確実に減少し、プロジェクトは健全な状態に向かいます。問題に対する解決行動を迅速かつ確実に実行するためのコツを紹介しましょう。
『[ヒント76]情報に優先順位を付ける確かなやり方』では、プロジェクト内で吸い上げた情報に対し、いかに優先順位を付けるかについて考えました。今回は優先順位が付いた情報をいかに解決していくかを取り上げます。もちろん、解決する順番は、トリアージによる優先順位(重要度)が高いものからです。具体的には、どうやって解決していけばよいでしょうか。
解決策がなかなか出てこなくて、困ってしまった場合、一番まずいのは考えすぎて行動に移れず、問題の解決速度がスローダウンしてしまうことです。解決策が見つからないと暗い気分になりますが、一歩一歩進むことで、ポジティブな発想を引き出すことが、困難な状況を打開していく鍵になります。次のステップ1~5はその基本手順です。
(ステップ1)解決のゴールを描く
課題管理やリスク管理の現場でよく見かける過ちは、「何ができたら、それが完了したことになるのか」(完了基準)を明確にしないまま、議論や対応を進めてしまうことです。このような状態では、問題はなかなか解決しません。まず「問題が解決した状態」とはどのような状態なのか、どうなっていれば解決したと言えるのかをよく考えることが大切です。
この時、完了基準だけでなく、解決した時に関係するステークホルダーがどういう状態になっているのかを併せて考えましょう。こうすることで、解決行動を導きやすくなります。
ステークホルダーがどのような形であれ「Yes」と言ってくる結果になればよいのか、それとも気持ちよく解決策に賛同してくれる方がよいのか。それによって、その後の関係や業務のやり取りも変わってきます。つまり、その問題に関わるステークホルダーにとって、どのような解決であればよいのかを考えることが重要なのです。まずはそれを考えながら、ゴールのイメージを描きます。
内容が複雑だったり、問題解決のゴールが遠く感じられるようなら、これが解決したら「上司からよくやったと褒められる」とか、「同じチームの人に感謝される」「重荷がなくなってスッキリし、職場に来るのが楽しくなる」など、ポジティブな視点で解決後の状態を想像してみましょう。そうすると、問題解決に対して前向きな解決策が思い付くことがあります。
(ステップ2)現状をスケーリングする
解決しなければならない問題が大きかったり難易度が高かったりすると、「到底解決できない」と初めからさじを投げたくなる場合があります。そんな時は、解決後のイメージをポジティブに想像したうえで、それを「10」の状態と仮定してみます。さらに、全く解決していない状態を「1」とします。では、現状はどのレベルにあるのかを考えてみることにします。
このようなやり方を「スケーリング」と言います。スケーリングしてみると、「到底解決できない」と思うような難しい問題でも、全く進んでいない「1」の状態ではなく、「2」や「3」である場合が意外と多いことに気づきます。こうすることで、現在の位置をより客観的に再認識でき、その後の解決行動が思い付きやすくなります。
次に、スケーリングした結果、「どんな理由でその値になったのか」を考えてみます。つまり、現状が「1」ではなく、意外にも「2」や「3」だと思った理由を明確にするのです。このような視点を持つことで、全体としては解決に向かって進んでいるように見えなくても、あまり気づいていなかった部分で進んでいることを再認識できます。
「Aチームが頑張っているので、そこでの検討が進めば少し解決策が見えてくる」といったことに改めて気づくかもしれません。この場合、できていないことではなく、「できていること」に目を向けます。なぜなら、できていないことに注目すると、せっかくポジティブな視点で考えていたものが、「やはりこの問題を解決するのは難しい」と思ってしまい、逆戻りしてしまうからです。これでは問題解決のスピードは上がりません。
「ゴールの状態まで、あと8もある」と考えると遠く感じられますが、反対に「できている部分が2もある」と考えれば前向きに捉えることができます。単純なことですが、この違いがもたらす心理的な効果は大きく、「意外にできている」と気づけば、解決行動を思い付きやすくなります。
(ステップ3)役に立ちそうなリソースを探す
スケーリングの結果、現状は「2」だとしても、それを「3」にするために役立ちそうなことはないかと考えるのも効果的です。「隣のチームのYさんは経験豊富なので、解決に役立ちそうなアドバイスをくれるかもしれない」とか、「N君はこの分野に詳しいので、手が空いたら応援を頼もう」といった発想が生まれるかもしれません。このように、解決に役立ちそうなリソース(モノ・ヒト・コト)を探すことで、具体的な解決策に結び付けます。
解決に役立ちそうなリソースを探してもなかなか思い付かない場合には、過去に似たような問題を解決した時のことを思い出してみましょう。その時、自分や仲間はどのようにして解決したのか。何が役に立って、解決に向かったのか。過去だけではなく、現在のプロジェクトでうまく回っているチームや作業プロセスに解決のヒントがないかを考えます。
(ステップ4)解決に近づく「小さな行動」
ここまできたら、スケーリング結果の数字を1つ上げるためにできそうなことを考えます。ただ、欲張ってはいけません。あくまで、スケールを1つ上げるために実行する「小さな解決行動」を考えましょう。
スケーリングの結果を一気に4つも5つも上げようとすると、ハードルが高く感じられ、なかなか実行可能なアイデアが出てきません。ですが、「1つゴールに近づくためには」と考えると、心理的なハードルは下がり、解決行動のアイデアが出やすくなります。
ゴールに至る全てのステップを、最初から思い描く必要はありません。この段階で強く意識してもらいたいのは「すぐにできそうなこと」であり、それを「やってみること」。あれこれ考えるだけで前に進まないよりは、「何か前に進みそうだと思ったことを実行に移してみる」のです。
(ステップ5)振り返りと繰り返し
解決行動を実行に移した後は、結果を振り返ってみます。そしてステップ1~5を繰り返し実行します。行動した結果、「ゴールに対してどこまで進んだか」「スケールが前回と比べてどこまで進んだか」を確認します。何が良かったのか、役立ちそうなリソースは他にないかを考え、さらにスケールを1つ進めるためにできる小さな解決行動を探します。これを繰り返すことで、1歩1歩ゴールに近づいていきます。
こうすると、意外なことが起こる可能性があります。行動する前は1つ進むと思っていたことが、振り返ると2つ、3つ進んでいるように感じられる場合があるのです。そうなると、次の行動も当初思っていたものと違うものになることがあります。
解決行動に「対応漏れ」がないかを確認
ここまでは、具体的な解決策がなかなか見つからない時、問題の解決速度を高める方法を紹介しました。後半は、解決策が分かっていながら、実際には行動に結び付かないケースへの対処法を考えます。解決策が見えている場合、その解決行動は「期限と担当者を明確にすること」で確実に実行できるようになります。現場でうまく実践できていれば、「問題の発生速度 < 問題の解決速度」という健全な状態を維持できるでしょう。
対応策が明確になったら、それをWBSやTo Doリストに記入します。そうすれば課題管理表の対応履歴を追わずとも、実行すべき行動(解決策)が行われているかを判断できます。あるいは、課題管理表をアレンジして、行動と期限、担当者が一目瞭然となる形で管理してもよいでしょう。いずれにせよ、解決行動が埋もれてしまわないよう、管理面での工夫が大切です。
ここでWBSやTo Doリストを再チェックします。期限や担当者が決まっていないタスクはないでしょうか。WBSの作成時に期限や担当者を考えず、とりあえずタスクだけを洗い出したけれど、結局そのままになっている、という「割り当て漏れ」はよく起こります。新規に追加したタスクに、期限と担当者を割り当てないまま放置している場面もよく見かけます。このようなタスクに対し、確実に期限と担当者を設定します。
次に「期限オーバー」のタスクを見過ごしていないかチェックします。期限が過ぎてしまっているのに、未対応のまま放置されているタスクがあれば、課題管理の意味がありません。WBSやTo Doを利用する時は、定期的に全体を見渡して、期限や担当者が設定されていないものがないか、期限を過ぎてしまっているタスクはないかをチェックする習慣が大切です。
担当者を設定したものの、その人が忙しすぎて対応できない場合もあるでしょう。当初設定した期限より少し遅れても大丈夫な場合や、逆に早めに実施すべき状況に変化する場合もあります。これらのケースでは、常に期限や担当者を変更して現状に合ったものにしておきます。
