- ホーム
- プロジェクトマネジメントのヒント
- プロジェクトを失敗させないヒント81『標準化が定着しない理由』
プロジェクトを失敗させないヒント81『標準化が定着しない理由』
『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』とは
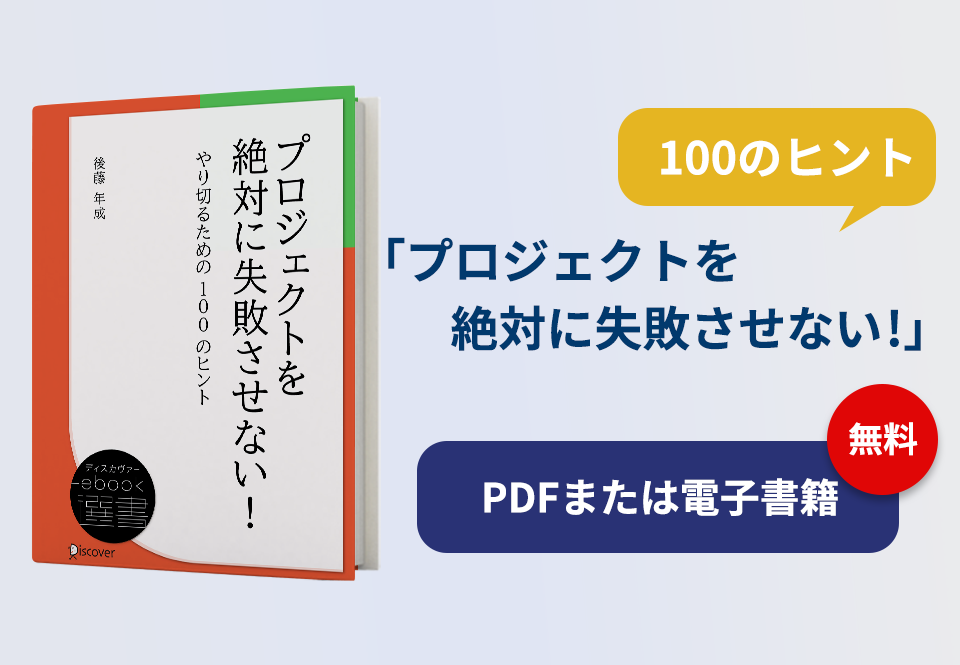
本記事は、プロジェクトを成功させるために必要なノウハウを、数百の支援実績経験をもとに記述した『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』より、 1つずつヒントをご紹介していく企画です。プロジェクトマネジメントについて、何らかの気づきを得るきっかけになれば幸いです。
当社はプロジェクトマネジメントの知識と経験を有し、皆様のプロジェクトが成功するお手伝いをさせていただいております。 プロジェクトマネジメントに関する疑問や課題がある方、成功への道筋をお探しの方、どうぞお気軽にご連絡ください。
お問合せはこちらからどうぞ。
※『プロジェクトを絶対に失敗させない!やり切るための100のヒント』をPDFまたは電子書籍でダウンロードできます
システム開発の現場には、システム開発標準やプロジェクトマネジメント標準など、様々な「標準」があります。プロジェクトでは、それらの標準に沿った運営が求められます。しかし、実際のところ、それらの標準は本当に現場のためになっているでしょうか。疑問に思うことが多々あります。
システム開発における標準化と聞いて、みなさんはどんなイメージを思い浮かべますか。「システム開発を効率よく進めるために有効なもの」と答える人もいれば、「実利のない、面倒くさい手続きばかりで生産性を下げるもの」「品質を確保するために必要なのは理解できるが、ここまでやるべきか腑に落ちない」など様々な意見があると思います。一般に、システム開発における標準化のメリットとデメリットは、以下のように5つずつ挙げられます。
<システム開発における標準化のメリット>
(1)関係者が同じ言葉を用いることで、コミュニケーションロスが少なくなる
(2)同じ標準を用いて開発したシステムとの比較ができる
(3)標準を改善していくことで、より効率よく高品質なシステムを開発できる
(4)アウトプットとして同じ品質が期待できる
(5)サンプルやテンプレートを利用することで、開発プロセスや成果物の検討時間を短縮できる
<システム開発における標準化のデメリット>
(1)標準が絶対的なバイブルになり、柔軟性がなくなる
(2)「標準に従っていればいい」という甘えの心理を生み、改善意欲を失う
(3)標準通りに実施した結果、現場の生産性が下がる
(4)利用もしない無駄な指標を計測し続ける
(5)プロジェクト固有の習慣や文化、言葉などを標準に合わせるための“翻訳作業”が発生する
システム開発現場の視点から単純に標準化を見た時、メリットだけを見ると、まるで魔法の杖のように思えます。半面、現実に標準化を取り入れたからといって、必ずしもプロジェクトに定着するとは限りませんし、プロジェクトが成功するわけでもありません。なぜでしょう。各々のプロジェクトが独自の目的や制約を持っており、全く同じプロジェクトなど存在しないためなのです。
同じプロジェクトは1つとして存在しないという前提
客観的に見て、定型でないプロジェクトに標準を無理やり当てはめ、「標準通りに全てやりなさい」と押し付けても、うまくいきません。一生懸命に標準を作っても、あまり適用されなくなってしまう理由はそこにあります。本来、標準をそのまま適用したくても適用できないものなのです。
ここでPMOが標準化の導入に大きな役割を果たします。それは、標準をテーラーメード(個別に仕立てる)してプロジェクトの形に合わせるという作業です。標準には「どのようなプロジェクトでも絶対に守らなければいけない普遍的なもの」と「プロジェクトの状況に合わせて変えてもよい、あるいは変えるべきもの」があります。例えば、会社として決めている「プロジェクトコストの計算方法」や法的規制に関わること、全体最適の面から標準化が必須なものは絶対に守らなければいけない普遍的なものです。
一方、課題管理や進捗管理の方法、変更管理のフロー、プロジェクト内での情報共有の方法は、プロジェクトの状況に合わせて変更しても構いません。簡略化あるいは省略しても標準化の目的を達成できるならそうすべきですし、逆に効率化のために作業やルールを追加すべき場面もあるでしょう。
図15◎管理手段の要件 重要なのは、2つのバランスを取りながら標準化を進めるべきだということです。2つの目的とは、「上位のマネジャーが必要としている標準化された情報を提供すること」と「現場のメンバーが効率よく作業を進められる仕組みを定着させること」です。PMOは時として、現場からの情報を上位層が必要とする情報へと“翻訳”してあげる役割を担うこともあります。
重要なのは、2つのバランスを取りながら標準化を進めるべきだということです。2つの目的とは、「上位のマネジャーが必要としている標準化された情報を提供すること」と「現場のメンバーが効率よく作業を進められる仕組みを定着させること」です。PMOは時として、現場からの情報を上位層が必要とする情報へと“翻訳”してあげる役割を担うこともあります。
PMOとして標準のテーラーメードを実施する際には、以下の4点に気を付けるとよいでしょう。
(1)手段であるはずの標準化が目的化してしまわないこと
(2)現場の規模や状況を無視した理想論を掲げないこと
(3)現場のリーダーやメンバーの負荷を著しく増やさないこと
(4)導入する作業や仕組みについて現場の理解を得ること
P.F.ドラッカー氏は著書『マネジメント 基本と原則』の中で「管理手段の要件」として7つのポイントを挙げています(図15)。これは、標準化という管理手段のエッセンスと言えるでしょう。PMOにとっても大いに参考になりますので、記憶にとどめておいてください。
